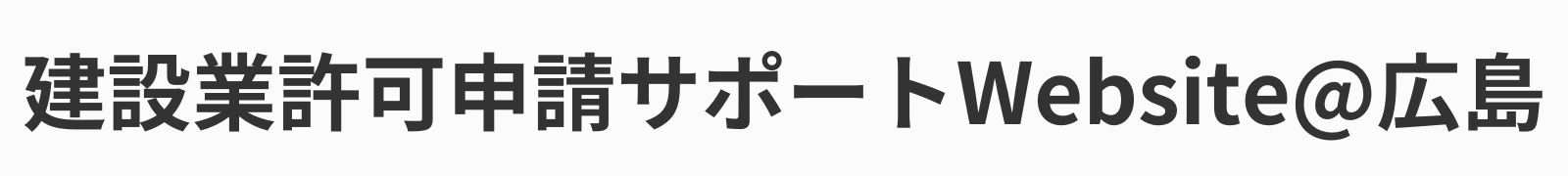本稿では、建設業の許可を受けるために、備えていることが求められる建設業法第7条の「許可要件」や、該当しないことが求められる同法8条の「欠格要件」等について解説いたします。
どのような場合に建設業許可が必要となるのか?

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。(いずれの場合も、取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。)
工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
※木造:建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
※住宅:住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
※木造:建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
※住宅:住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
建設業許可の要件
建設業の許可を受けるためには、次の6つの要件をすべてクリアしていることが必要です。
- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力
- 適切な社会保険等に加入していること
- 営業所技術者等
- 誠実性
- 財産的基礎等
- 欠格要件等
要件1 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力
建設業許可の「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」とは、建設業を適切に経営できる能力を持つ人材が会社にいることを求める要件です。法人の場合は役員のうち常勤である人が、個人事業主の場合は事業主または支配人が、次のいずれかに該当する必要があります。(常勤役員等の設置)
(1) 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験がある者。
(2)建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験がある者。(経営業務を執行する権限の委任を受けた人のみ。)
(3)建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験がある者。
(4)常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者で、かつ、財務管理の業務経験がある者、労務管理の業務経験がある者及び業務運営の業務経験がある者を、当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くこと。
①建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験がある者。
②5年以上役員等としての経験があり、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験がある者。
要件2 適切な社会保険等に加入していること
令和2年10月1日以降、適切な社会保険・雇用保険へ加入することが許可要件となっています。
・健康保険
・厚生年金保険
・雇用保険
要件3 営業所技術者等
建設工事の適切な施工を確保するために、建設業を営もうとする営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(営業所技術者等)を専任で設置する必要があります。一般建設業許可の場合は営業所技術者、特定建設業許可の場合は特定営業所技術者と呼ばれ、それぞれ要件が異なります。
一般建設業許可の場合
① 指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
② 指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
②ー1 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
②ー2 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称する者
→ 指定学科一覧へ
③ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
④ 国家資格者
⑤ 複数業種に係る実務経験を有する者
要件4 誠実性
当該法人、その役員等、個人事業主、支配人、支店長、営業所長が、請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないことが必要です。
要件5 財産的基礎等
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は、金銭的信用を有していることが必要で、次のいずれかに該当することが必要です。一般建設業許可と特定建設業許可で要件が異なります。
一般建設業許可の場合
(1)自己資本の額が500万円以上あること。
(2) 500万円以上の資金を調達する能力があること。
(3)許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること。
要件6 欠格要件等
許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。
*国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の①から⑭のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあっては、①又は⑦から⑭までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。
①破産者で復権を得ないもの
②第29条第1項第7号又は第8号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
③第29条第1項第7号又は第8号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
④前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
⑤第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑦禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑧この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑨暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(⑭において「暴力団員等」という。)
⑩精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
⑪営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに①から④まで又は⑥から⑩までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの
⑫法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑩までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、⑥に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
⑬個人で政令で定める使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑩までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、⑥に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
⑭暴力団員等がその事業活動を支配する者
※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事等
・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者
まとめ

以上、建設業許可の要件について解説させていただきました。最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。
当事務所では、広島市を拠点として、建設業許可に関する各種手続きのサポートを行っております。建設業許可や建設業法に関するご相談がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
お客様に代わって複雑で面倒な手続きをサポートいたします!